
YouTube・Jun Osuga
ワールドワイドに向けた、音楽家としてのチャンネル。オーセンティックなシンセサイザーサウンドを核にした楽曲を配信中。
YouTubeチャンネルにアクセス

X(大須賀 淳)
個人アカウント。情報発信から私的なつぶやきまで、随時ポスト中。
Xでフォローする

X(Jun Osuga)
ワールドワイド向けの音楽活動アカウント。楽曲の動画を多数発信中。
Xでフォローする

小林よしのり全宇宙
ブログ記事執筆を担当。連日更新中。
ブログを読む
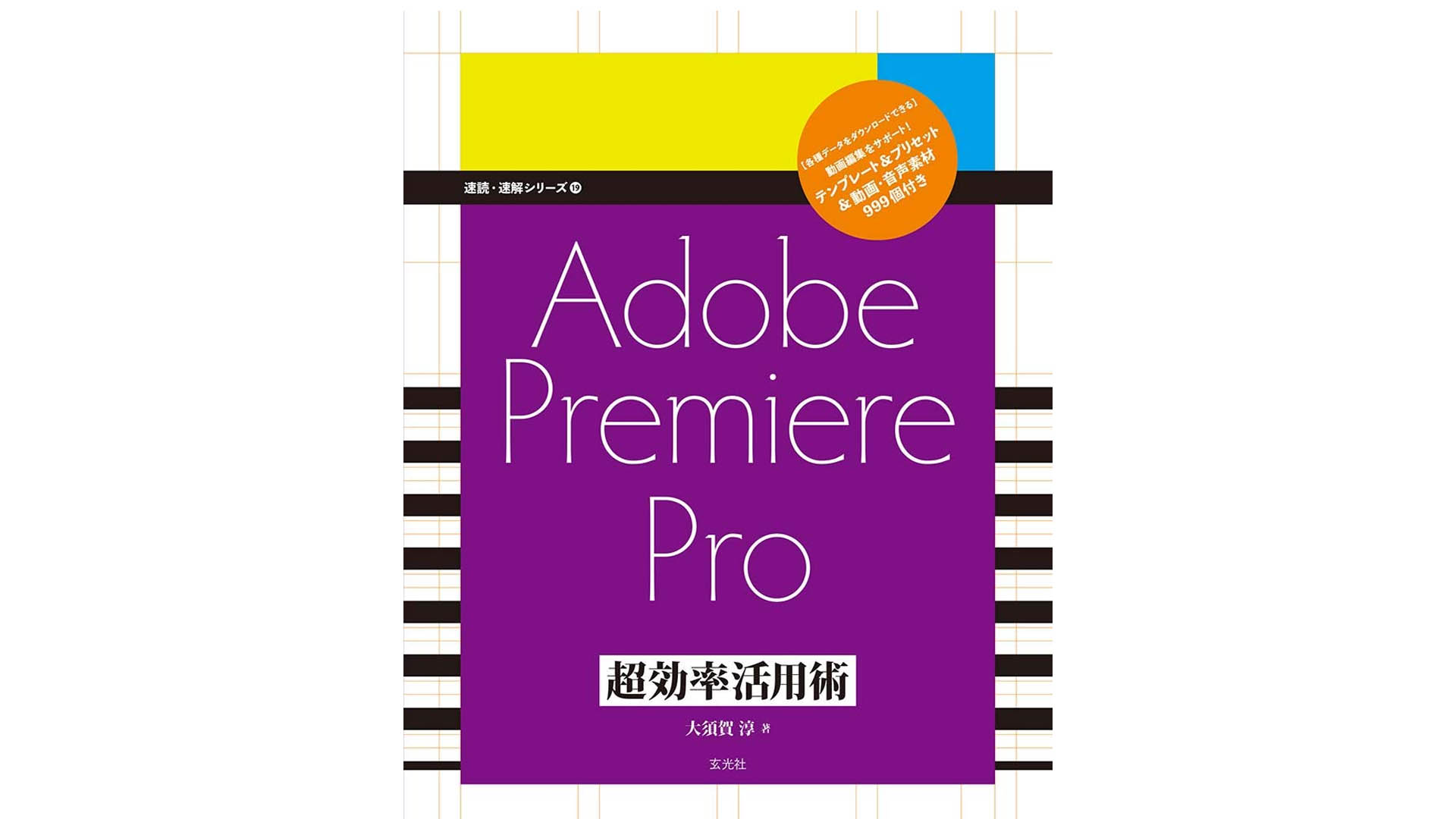
「Adobe Premiere Pro 超効率活用術」用データ
書籍の付録データはこちらからダウンロードしてください。
ダウンロードする